「高校なんて行きたくない」
「勉強したくない。意味ないじゃん」
そんな言葉を子供に言われたとき、
心の中がザワッと揺れる親御さんは多いと思います。
「このままで将来大丈夫なの?」
「進学しないなんて、人生を諦めてない?」
──そう思うのは、当然のことです。
私も3人の子を育てる父親であり、児童福祉の現場で10年以上、
“勉強嫌い”や“不登校”の子どもたちと向き合ってきました。
そこで強く感じるのは、
**「高校に行きたくない」と言う子ほど、“心が疲れている”**ということ。
この記事では、
「進学したくない」「勉強嫌い」という言葉の“本当の意味”を心理学・脳科学の視点で紐解きながら、
親としてどう寄り添えばいいのかを、現場のリアルな経験を交えてお伝えします。
「高校に行きたくない」子供の心理とは?
① 「勉強が嫌」ではなく「自分に自信がない」
多くの子が「高校行きたくない」と言うとき、
実は“やりたくない”ではなく、“できない自分がイヤ”なんです。
長年、放課後等デイサービスで思春期の子どもと関わる中で、
「勉強嫌い」と言う子のほとんどが、実際は“自己肯定感が低下”していました。
「どうせ自分は頭悪い」
「やっても無理」
──こうした言葉の裏には、失敗体験の積み重ねがあります。
テストで点が取れない、先生に叱られた、友達にバカにされた。
そうした経験が「勉強=苦痛」と脳に刷り込まれていくのです。
② 勉強=親との関係になっている
「勉強しなさい!」
「高校くらい行かないと困るよ!」
親が心配で言えば言うほど、子供の中では“勉強=親との戦い”になります。
脳科学では、感情の中枢である扁桃体が“脅威”を感じると、
論理的思考を担う前頭前野の働きが一時的に低下します。
つまり、叱られると考える力が止まるんです[LeDoux, 2014]。
関連記事おすすめ
勉強嫌いの裏にある“脳と心のサイン”
① 扁桃体(不安脳)が過剰に反応している
「勉強=不安」「失敗=怖い」と感じると、
脳内でストレスホルモン(コルチゾール)が分泌され、
集中や記憶を司る海馬の働きを抑制します[Lupien et al., 2009]。
その結果、やる気が出ない・覚えられない・眠いなどの反応が出ます。
② セロトニン不足による「無気力」
セロトニンは“心の安定ホルモン”。
睡眠不足や運動不足が続くと、この物質が減少し、
気分の落ち込みや無気力感が強くなります。
つまり、「勉強したくない」=脳のエネルギー切れなんです。
関連記事おすすめ
親が焦ると、子供はますます動かなくなる理由
① 焦りは“伝染”する
親の「なんで勉強しないの!」という焦りは、
子供の神経系にもダイレクトに伝わります。
研究では、親のストレスレベルが高い家庭ほど、
子供のストレスホルモンも上昇する傾向があると報告されています[Gunnar & Donzella, 2002]。
親が落ち着くことで、子供の扁桃体も落ち着く。
まずは「親の安心感」こそ最高のサポートなのです。
② “正論”より“共感”が動かす
「高校は行った方がいい」「将来困るよ」という正論は、
思春期の子にはほとんど響きません。
なぜなら、彼らは「理解」より「共感」を求めているから。
「そう感じるんだね」
「無理しすぎてるのかもしれないね」
たった一言でも、“理解された”と感じることで、
子供の心にエネルギーが戻ります。
関連記事おすすめ
「進学しない選択」を考える前に話してほしい3つのこと
① 「行かない」ではなく「どうしたい?」を聞く
進学を拒否する言葉の裏には、
「何かをやりたい」よりも、「もう疲れた」というサインが多いです。
まずは「なんで行きたくないの?」ではなく、
「今、何に一番しんどさを感じてる?」と聞いてみましょう。
② “選択肢”を見せてあげる
高校=全日制だけではありません。
通信制・定時制・高卒認定など、
今は多様な学びの形が選べる時代です。
親が「道は一つじゃない」と伝えることで、
子供の脳は「自分にも未来がある」と感じ始めます。
③ 「あなたの人生を信じてる」と伝える
何より大事なのは、
「進学するかどうかより、あなたが幸せに生きてほしい」
と、親が“条件なしの信頼”を見せること。
この一言が、子供の心に“再起のエネルギー”を灯します。
関連記事おすすめ
勉強嫌いでも“自分で動き出す子”になる関わり方
① 「勉強=評価」ではなく「学び=成長」に変える
点数で一喜一憂すると、子供は“結果だけ”を見るようになります。
でも、「昨日より理解できたね」「考え方が面白いね」と
“プロセス褒め”をすることで、学ぶ楽しさが戻ってきます。
② 親が“学ぶ姿勢”を見せる
親が本を読む、ニュースを語る、資格を取る──
その姿こそ最高の教育。
「勉強=大人になっても使う力」と実感できます。
③「好きなことから」始めてOK
学びの入り口は“好き”でいいんです。
音楽、ゲーム、料理、野球…どんな分野でも、
「これを研究してみたい」に変われば、それはもう“勉強”。
子供の興味を学びに変えるのが、親のサポートです。
関連記事おすすめ
まとめ|高校進学より大切なのは「生きる力」
“高校に行く・行かない”は、人生のゴールではありません。
むしろ大切なのは、「自分で考え、自分で決める力」です。
子供が今どんな道を選んでも、
親が「信じて見守る」ことで、その選択は必ず意味を持ちます。
「高校に行きたくない」と言えるのも、
それだけ自分で考え始めている証拠。
焦らず、信じて、見守って。
親の“安心”こそ、子供が再び動き出すエネルギーです。
【関連記事】
【参考文献】
- LeDoux, J. (2014). Anxious: Using the brain to understand and treat fear and anxiety. Viking.
- Lupien, S. J., et al. (2009). Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. Nature Reviews Neuroscience, 10(6), 434–445.
- Gunnar, M. R., & Donzella, B. (2002). Social regulation of the cortisol levels in early human development. Psychoneuroendocrinology, 27(1–2), 199–220.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. American Psychologist, 55(1), 68–78.
- 厚生労働省. (2023). 子どもの進学・学習意欲と家庭支援に関する調査報告書. https://www.mhlw.go.jp/
まとめポイント
- 「高校に行きたくない」は怠けではなく“心のSOS”
- 勉強嫌いの背景には「自信のなさ」や「不安」がある
- 親の焦りは子供に伝染する。共感と安心を優先
- 「好きなこと」「小さな成功体験」から再スタート
- 高校進学よりも大切なのは、“自分で選ぶ力”
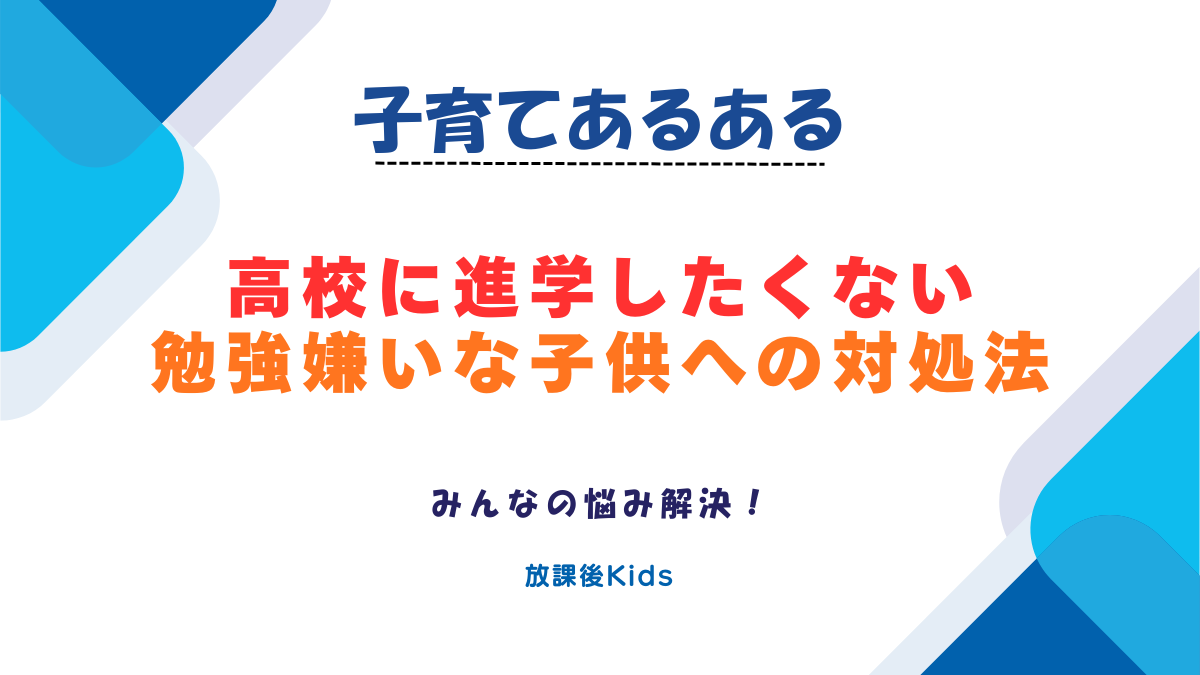
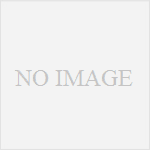
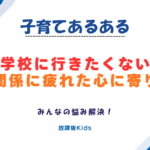
コメント