「友達に無視された…」
「グループに入れない」
「もう誰も信じたくない」
──そんな言葉を子供から聞いたとき、
親としてどう反応していいか迷いますよね。
「そんな子、気にしなくていいよ」と励ますほど、
子供が余計に落ち込むこともある。
でも、焦らなくて大丈夫です。
人間関係で傷ついた子供の心は、“安心”でゆっくり回復していくからです。
10年以上、対人ストレスを抱えた子供たちと関わる中で感じたのは、
「家庭が“安全基地”になるだけで、子供の回復力は驚くほど強くなる」ということ。
この記事では、
「どう声をかける?」「何をしてはいけない?」という具体的な関わりを、
脳科学・心理学の裏付けとともに丁寧に紹介します。
子供が人間関係で傷ついたときに起こっていること
① 脳は“危険”を記憶する
脳には「痛みを避ける」仕組みがあります。
人からの拒絶や仲間外れなどの社会的痛みは、
実際に身体の痛みと同じ神経経路(前帯状皮質)を刺激します[Eisenberger, 2012]。
つまり、
「友達に無視された」=「殴られた」と同じくらいのストレス反応が起きている。
そのため、子供は無意識に「人が怖い」「また傷つくかも」と感じてしまいます。
② 自己肯定感が一時的に下がる
人間関係のトラブルは、
「自分が悪いのかも」と思い込ませやすい。
このとき、自己肯定感(=自分を信じる力)が一時的に低下します。
心理学では、これを帰属理論と呼び、
子供が「内的要因(自分のせい)」に原因を求めすぎると、
無力感が強まり、自信を失ってしまうことがわかっています[Weiner, 1985]。
関連記事おすすめ
親がついやってしまう“逆効果”の対応
① 「そんなの気にしなくていい」
励ますつもりでも、この言葉は子供にとって
「気持ちを否定された」と感じやすい。
傷ついたときほど、子供は“理解してほしい”と願っています。
気持ちを軽く扱われると、「どうせわかってもらえない」と心を閉ざしてしまいます。
② 「相手も悪気なかったんじゃない?」
相手を庇う言葉も逆効果です。
子供は「味方がいない」と感じ、安心感を失います。
まずはどんな気持ちを抱いたのかを聞くことが先。
正しさより、共感を優先することが信頼回復の第一歩です。
③ 「なんで言い返さなかったの?」
行動を責めるような言葉は、
「自分が弱いせい」と罪悪感を生みます。
「怖かったんだね」「びっくりしたね」
──これだけで、子供は“守られた感覚”を取り戻します。
関連記事おすすめ
自信を取り戻す3つの家庭サポート法
① 「共感」と「見守り」で脳を安心させる
脳科学では、人が“理解された”と感じた瞬間、
オキシトシンという安心ホルモンが分泌されることがわかっています。
オキシトシンはストレスホルモン(コルチゾール)を抑え、
自己肯定感を回復させる働きがあります[Heinrichs et al., 2009]。
「それはつらかったね」
「そんなことがあったら、悲しくなるよね」
この“共感の言葉”が、子供の脳に“安全信号”を送ります。
② 小さな成功体験を積ませる
傷ついた子供は、“自分に価値がある”という感覚を失っています。
勉強やスポーツでなくても構いません。
・料理を手伝って「助かった」
・家の植物に水やりして「ありがとう」
・兄弟を笑わせて「優しいね」
こうした小さな貢献感が、脳内ドーパミンを活性化し、
自信を再構築していきます[Bandura, 1997]。
③ 「人は変えられないけど、自分の感じ方は変えられる」
最終的に、子供が立ち直るためには“自己効力感”が鍵になります。
「また誰かに嫌なこと言われても、どう感じるかは自分で選べる」
この考え方を、少しずつ伝えていくことで、
他人に左右されない心の軸が育ちます。
関連記事おすすめ
我が家で実践して効果があった「心を整える習慣」
うちの次男(当時9歳)も、友達とのトラブルで「学校行きたくない」と言ったことがあります。
私はすぐに解決策を言わず、
まず「今日はパパと散歩しよう」と誘いました。
歩きながら他愛ない話をしていると、
彼がポツリと「本当は悲しかった」と。
その瞬間、私は何も言わずに「そっか…」とだけ返しました。
すると彼は泣いて、そして笑いました。
その日の夜、彼が言ったのは、
「明日、行ってみる。友達と話してみる」
“解決”は親が導くものではなく、
安心が整ったとき、子供が自分で見つけるものなんです。
関連記事おすすめ
まとめ|「もう一度信じてみよう」と思える環境を
人間関係で傷ついた子供は、
心のどこかで「もう信じるのが怖い」と感じています。
親ができるのは、
「あなたを信じてる」というメッセージを
毎日の小さな関わりの中で伝え続けること。
傷ついた経験は、心を強くする“肥料”になる。
ただし、それを育てるのは“安心という土壌”です。
焦らず、寄り添いながら、
子供の中に“もう一度人を信じてみよう”という気持ちが芽生えるのを待ちましょう。
【関連記事】
【参考文献】
- Eisenberger, N. I. (2012). The neural bases of social pain: Evidence for shared representations with physical pain. Nature Reviews Neuroscience, 13(6), 421–434.
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.
- Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92(4), 548–573.
- Heinrichs, M., et al. (2009). Social support and oxytocin interact to suppress cortisol and subjective responses to stress. Biological Psychiatry, 54(12), 1389–1398.
- 厚生労働省. (2023). 子どもの人間関係とメンタルヘルス支援に関する報告書. https://www.mhlw.go.jp/
まとめポイント
- 「人間関係の傷」は脳にとっても“痛み”と同じ
- 「気にしなくていい」より“共感”が回復の第一歩
- 家庭での安心・貢献・小さな成功体験が自信を再構築
- 親が「信じてる」と伝えることで、再び他者を信じる力が育つ
- 立ち直り力=“安心 × 自己効力感 × 経験の整理”
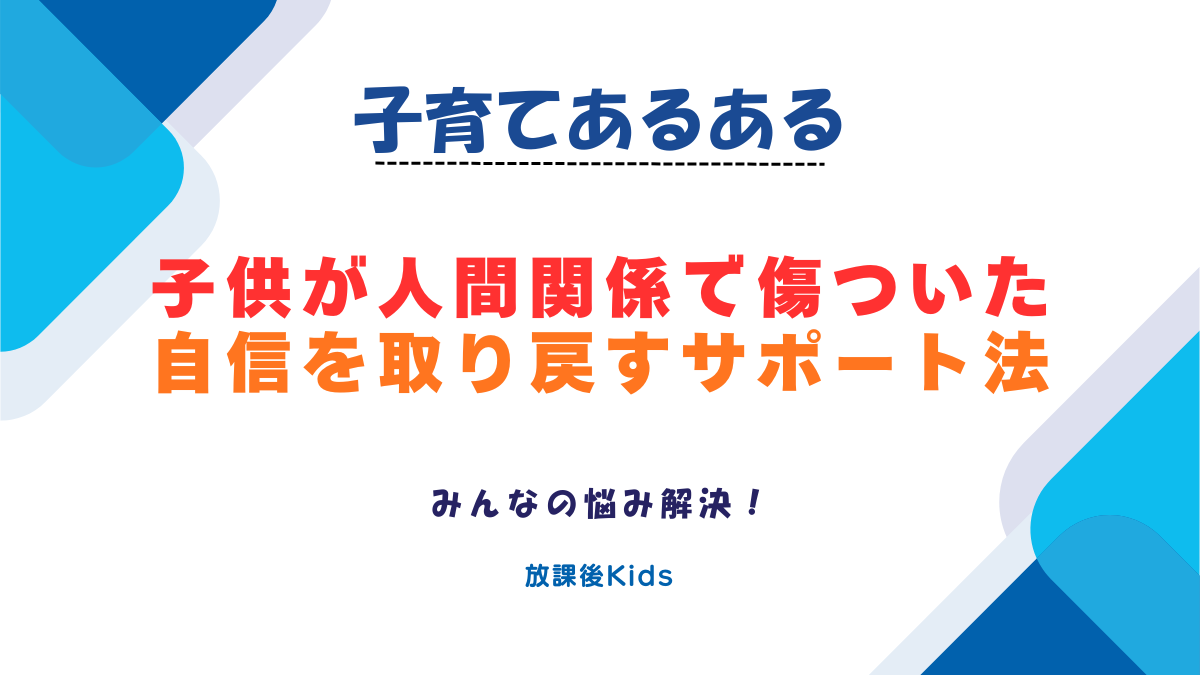
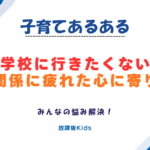
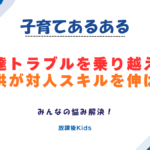
コメント