「朝になるとお腹が痛い」
「友達といるのがしんどい」
「もう学校行きたくない」
──そんな言葉を子供から聞いたとき、
親としては胸が締めつけられますよね。
「何かあったの?」「誰かに嫌なことされた?」と聞いても、
「別に…」と答えない子も多い。
でも、私はこう思うんです。
学校に行きたくないという言葉は、“心の防衛反応”です。
10年以上、児童支援や心理相談の現場で
対人関係に悩む子供たちと関わってきました。
そこから見えてきたのは、
“子供の心が限界を迎える前に出す小さなSOS”を、
親がどう受け止めるかで未来が変わるということ。
この記事では、
「学校に行きたくない」と言う子の心理を深掘りしながら、
親が今すぐできる“心を守る関わり方”をお伝えします。
「学校に行きたくない」子供の本当の理由
子供が「行きたくない」と言う理由は、
大きく分けて3つあります。
① 対人関係のストレス(友達・先生)
「友達とうまく話せない」
「グループに入れない」
「先生に怒られるのが怖い」
こうした人間関係の摩擦が続くと、
子供の脳は“学校=危険な場所”と認識します。
心理学では、これを条件付け回避反応と呼びます。
つまり、
「嫌なことが起きる場所には行きたくない」──これは自然な防衛反応なんです。
② 感情のコントロールが難しくなっている
学校では、1日中「人に合わせる」必要があります。
子供の脳(特に前頭前野)はまだ発達途中のため、
ストレスが続くと感情を整理する力がオーバーヒートします。
その結果、
「朝起きたら泣けてきた」「理由がわからないけど行けない」
という状態になるのです[Diamond, 2013]。
③ 家では頑張りすぎている
意外と多いのが、「家ではいい子」タイプ。
外で気を張りすぎて、家でようやく“本当の自分”に戻る子です。
家での「学校行きたくない」は、
実は“信頼してる人にしか見せられない弱音”なんです。
関連記事おすすめ
対人関係ストレスが脳と心に与える影響
① ストレスで扁桃体が過活動になる
「また何か言われるかも」「昨日のことを思い出す…」
──このような心配が続くと、扁桃体(不安中枢)が常にON状態になります。
すると、
・胃痛・頭痛・吐き気
・登校直前の涙
・朝だけ体調不良
など、身体反応として出ることが多いです[LeDoux, 2014]。
② セロトニン・オキシトシンの低下
人との触れ合いや安心感が減ると、
心を落ち着ける脳内物質(セロトニン・オキシトシン)が低下します。
この状態では、
「人が怖い」「一人が落ち着く」と感じやすくなります。
関連記事おすすめ
親の対応で子供の回復が変わる
① 「行かせよう」とするほど逆効果
親が焦って「なんで行かないの」「行かないとダメでしょ」と言うと、
子供は“理解されない”と感じて心を閉ざします。
心理学では、これを二次的ストレスと呼びます。
学校のストレスに加えて「家庭でもプレッシャー」が増えることで、
回復が遅れてしまうのです。
② “共感”が回復のスタートライン
「行きたくない気持ち、わかるよ」
「無理しなくていいよ」
この一言が、子供の脳に「安全」を伝えます。
安全を感じたとき、扁桃体の反応が落ち着き、
考える力(前頭前野)が戻ってくるのです。
③ 休む=逃げではなく、心の充電
「休む」と聞くと、親は不安になりますよね。
でも、子供にとって“学校から離れる時間”は、
自分を取り戻す時間でもあります。
休息は“立ち止まる勇気”であり、次の一歩を準備する行動です。
📎関連記事おすすめ
「学校に戻す」より「安心を取り戻す」ステップ
① まずは「安心ループ」を作る
子供が笑える時間・落ち着ける場所を確保すること。
家庭で安心できる時間が増えるほど、
“外に出る力”は自然と戻ってきます。
親子で散歩する・一緒に料理する・動物に触れる
──これだけでもセロトニンが増え、気持ちが安定します。
② 学校以外のつながりを持たせる
不登校=孤立ではありません。
地域のフリースクール、通信教育、オンライン学習など、
学ぶ場所は一つじゃないことを伝えましょう。
③ 「いつから行く?」より「どんな気持ち?」
登校再開を急ぐより、
「今日どうだった?」「何が一番つらい?」と
気持ちの整理をサポートする方が、はるかに効果的です。
関連記事おすすめ
我が家で実践して効果があった関わり方
私の長男(当時小4)も、一時期「学校行きたくない」と言ったことがあります。
理由を聞くと、「友達に無視された気がする」とのこと。
私はまず、「無理に行かなくていいよ」と伝え、
一緒に図書館に行きました。
静かな時間の中で、彼はポツリとこう言いました。
「あの子に何か言われたわけじゃないけど、怖い。」
この瞬間、私は気づきました。
子供は言葉にできない不安を抱えている。
親の役目は“問い詰める”ことではなく、“安心できる空間を守る”ことだと。
数日後、彼は自分から「今日は行ってみようかな」と言いました。
──それが、子供の心の回復のサインです。
関連記事おすすめ
まとめ|“休む勇気”は“生きる力”の始まり
「学校に行きたくない」と言うのは、
“逃げ”ではなく“心のSOS”。
対人関係で疲れた子供の脳と心を回復させるには、
安心・共感・信頼の3つが必要です。
焦らず、
「あなたが安心して笑えることが一番大事」と伝えてください。
学校は行く場所ではなく、成長する場所。
その前に“心が育つ時間”を大切にしてほしい。
【関連記事】
【参考文献】
- Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168.
- LeDoux, J. (2014). Anxious: Using the brain to understand and treat fear and anxiety. Viking.
- Gunnar, M. R., & Donzella, B. (2002). Social regulation of cortisol levels in early human development. Psychoneuroendocrinology, 27(1–2), 199–220.
- 厚生労働省. (2023). 子供のメンタルヘルス支援と不登校対応に関する報告書. https://www.mhlw.go.jp/
まとめポイント
- 「学校行きたくない」は“人間関係の疲れ”が多い
- 扁桃体の過活動で体調不良が出ることも
- “共感”が子供の脳を落ち着かせる第一歩
- 休むことは逃げではなく「回復のプロセス」
- 親の安心が、子供の安心をつくる
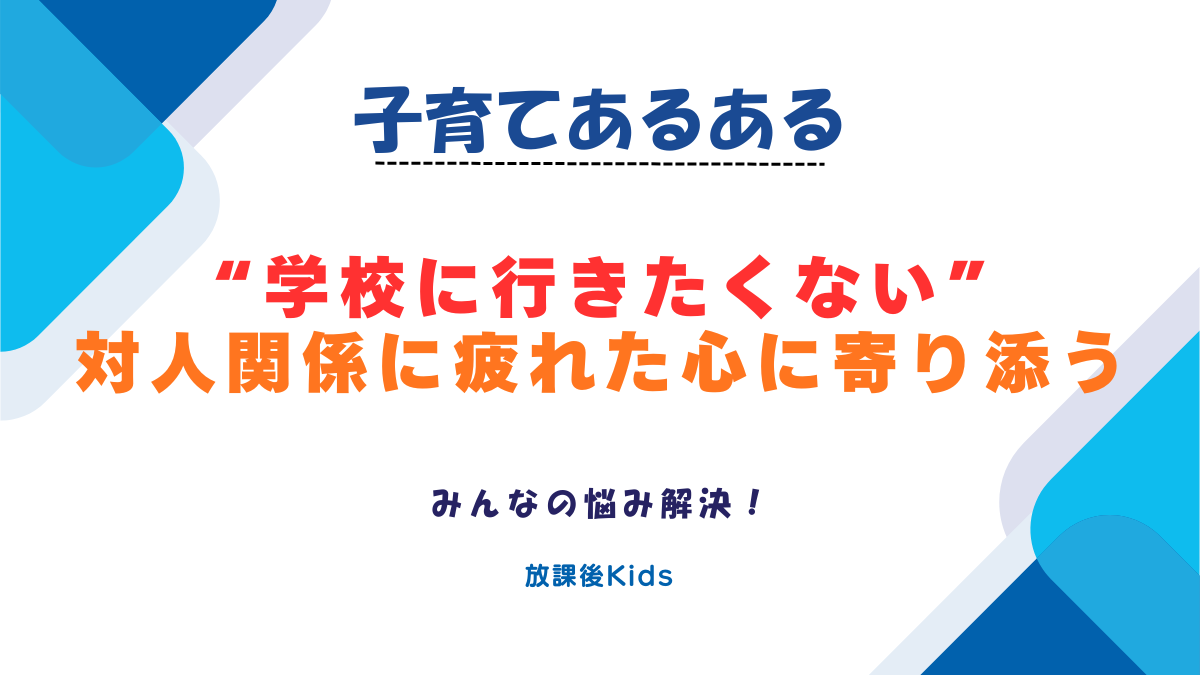
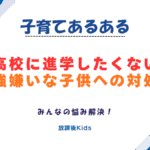
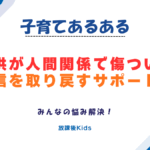
コメント