「テスト前なのに全然勉強しない!」
「ゲームばかりして、見てるだけでイライラする…」
──きっと、この記事を読んでいるあなたも、そんな気持ちではないでしょうか。
私も3人の子どもを育てる父親として、何度も同じ経験をしました。
そして10年以上、児童福祉の現場で“勉強が苦手な子”たちと関わってきて感じるのは、
「やる気がない=怠けている」ではないということです。
むしろ、テスト前に勉強したくなくなるのは、
脳と心が「オーバーヒート」しているサインなんです。
この記事では、
心理学と脳科学の根拠を交えながら、
「テスト前に勉強したくない子供が、どうすれば自然にやる気を取り戻すのか」
を、やさしく・具体的に・親目線でお伝えします。
なぜテスト前になると子供は勉強したくなくなるのか?
① プレッシャーで“脳が逃げモード”になる
テスト前というのは、大人で言えば「締め切り前」「プレゼン前」と同じ。
脳は緊張状態になり、扁桃体(恐怖・不安を司る部分)が過剰に反応します。
その結果、「逃げたい」「今は考えたくない」という防衛本能が働くのです。
脳科学者ジョセフ・ルドゥー(LeDoux, 2014)は、
「不安が強くなると、脳は思考よりも防衛を優先する」と述べています。
つまり、勉強から“逃げている”のではなく、
脳が自分を守っている状態なのです。
② 「完璧にやらなきゃ」がやる気を奪う
真面目な子ほど、「全部覚えなきゃ」「失敗したら終わり」と考えます。
でもその“完璧思考”こそが、やる気を奪う大きな原因です。
脳は“成功体験”を予測したときにドーパミンを出すのですが、
「どうせできない」と思った瞬間、その分泌が止まります。
「できる気がしない」=「脳が動かない」
やる気が出ないときは、怠けているのではなく、
脳がエネルギー節約モードに入っているのです。
③ “やらされ感”がモチベーションを下げる
心理学でいう「自己決定理論(Deci & Ryan, 2000)」によると、
人は“自分で選んで行動している”と感じるときに最もやる気が出ます。
しかし、
「勉強しなさい」「今すぐやれ」と命令されると、
脳は“自由を奪われた”と感じて反発(リアクタンス)を起こすのです。
関連記事おすすめ
「勉強しなさい」が逆効果になる理由
「うちの子、言わないとやらないから」と感じる気持ちは痛いほどわかります。
でも実は、“言えば言うほど”子供は動かなくなるんです。
これは心理学の「リアクタンス効果」。
“強制される”と、人はその反対をしたくなる。
「勉強しなさい!」→「今やろうと思ってたのに!」
まさにこの反応がそれです。
親が指示するほど、子供は「自分で選ぶ感覚」を失い、
やる気スイッチがOFFになります。
代わりに使える声かけ例
| NGワード | 言い換え例 |
|---|---|
| 「まだやってないの?」 | 「今日はどの教科から始める?」 |
| 「早く机に座って!」 | 「一緒に5分だけやってみようか」 |
| 「そんな点じゃ困るでしょ」 | 「次はどんなところを伸ばしたい?」 |
“命令”ではなく“提案”に変えるだけで、
子供の前頭前野(思考・判断の脳)が動き出します。
関連記事おすすめ
やる気が戻る“脳のリセット法”3選
① 10分休む(集中力の限界を超えない)
脳科学では、集中力は約40分が限界とされています。
疲れた脳で勉強を続けても、記憶はほとんど定着しません。
むしろ、10分の休息でドーパミンと血流が回復し、
再び集中力が戻ることが研究でわかっています[Diamond, 2013]。
コツ:
タイマーで「40分+10分」サイクルを親子で決めておく。
② 勉強する場所を変える
同じ部屋・同じ机だと、脳が「飽きた環境」と判断します。
たまにリビング・図書館・カフェなどを使うと、
新鮮な刺激で集中力が高まります。
③ ご褒美より“達成感”を重視
「○点取ったらゲームしていいよ」ではなく、
「ここまでできたね!」と過程を褒めること。
報酬よりも“できた自信”がやる気を長続きさせます。
関連記事おすすめ
テスト前の正しい声かけとNGワード
| シーン | NGな声 | OKな声 |
|---|---|---|
| 朝 | 「昨日もやってないじゃん!」 | 「昨日頑張ってたね。今日はどこをやろうか?」 |
| 勉強中 | 「まだ終わってないの?」 | 「区切りついたら一緒にお茶しよう」 |
| 結果後 | 「もっとできたでしょ」 | 「ここまでよく頑張ったね」 |
ポイント:
“結果”より“過程”を評価すると、子供の自己効力感が伸びます。
我が家でうまくいった「やる気スイッチの見つけ方」
長男が中学1年の頃、まさに“やる気ゼロ少年”でした。
テスト前も「どうせムリ」と投げやり。
私もつい、「勉強しろよ!」と言いたくなりましたが、
ぐっとこらえて、こう言いました。
「パパも隣で仕事するから、5分だけ一緒にやってみよう」
すると彼は渋々始め、5分後には「もう少しやる」と言い出しました。
この“自分でやる”感覚が、ドーパミンを動かす鍵なんです。
行動が感情を作る。
「やる気が出たらやる」ではなく、「やり始めたらやる気が出る」。
これが脳の基本法則です。
関連記事おすすめ
まとめ|“やる気がない日”も成長の一部
子供が勉強しない日は、親も不安で焦ります。
でも覚えておきたいのは、「休む」も学びの一部ということ。
脳も心も、休むことで記憶を整理し、次の意欲を生み出します。
焦らず、
「今日も頑張ってるね」「疲れてるね」と、
子供の“今”を受け止めてあげてください。
やる気がない日があるからこそ、
“自分で立ち上がる力”が育ちます。
【関連記事】
【参考文献】
- LeDoux, J. (2014). Anxious: Using the brain to understand and treat fear and anxiety. Viking.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168.
- 厚生労働省. (2023). 子供の学習意欲とストレスに関する調査報告書. https://www.mhlw.go.jp/
まとめポイント
- 「勉強しない=怠け」ではなく「脳の防衛反応」
- 命令より“提案”がやる気を引き出す
- ドーパミンは「やり始めてから」出る
- 親の“落ち着き”が、子供の“やる気”を育てる

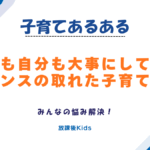
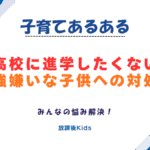
コメント