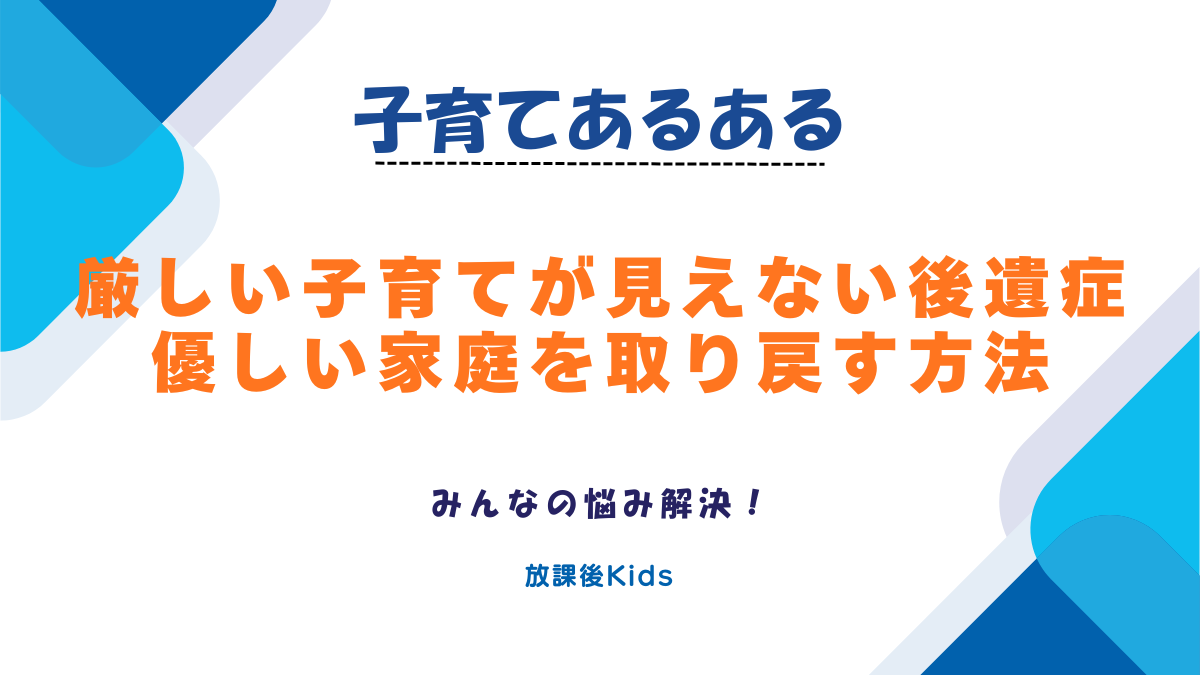
「こんなに怒るつもりじゃなかったのに…」
叱ったあとに後悔する──そんな経験、ありませんか?
「厳しく育てる=しっかりした子になる」と信じて頑張る親ほど、
実は子供の心のエネルギーを削ってしまっていることがあります。
10年以上、児童福祉の現場で“厳しい親のもとで育った子”を見てきて感じるのは、
彼らの多くが「正しさは知っているけど、自分に自信が持てない」という共通点を抱えているということ。
この記事では、
厳しすぎるしつけが子供の脳と心理にどう影響するのか、
そして「叱る」と「傷つける」の違いを明確にしながら、
今日からできる“やさしくて強い関わり方”をお伝えします。
なぜ親は厳しくしてしまうのか?
「ちゃんとしてほしい」愛情の裏返し
多くの親が厳しくしてしまう理由は、
“子供に幸せになってほしい”という深い愛情からです。
ただし、その思いが強すぎると、
「失敗させたくない」「周りに迷惑をかけさせたくない」といったコントロール欲求に変わりやすくなります。
実はこれ、心理学でいう「投影的期待」──
親の不安や理想が、子供への“過干渉”として表れる状態なんです。
関連記事おすすめ
厳しすぎる子育てが子供に与える心理的影響
① 自己肯定感が低くなる
厳しい環境では、子供は常に「正解かどうか」を気にするようになります。
すると、“間違える=ダメな自分”という思考が固定化し、
自己肯定感(=自分を信じる力)が低下していきます[Deci & Ryan, 2000]。
② 感情を表に出せなくなる
「怒られるくらいなら黙っておこう」という抑圧が続くと、
感情の表現力や共感力が育ちにくくなります。
結果として「何を考えているかわからない子」になるケースも少なくありません。
③ “条件付きの愛情”で育つ
「できたときだけ褒められる」「失敗したら怒られる」──
このような経験を繰り返すと、子供は「愛されるために頑張る」ようになります。
これが成人後の“承認依存”につながることも。
関連記事おすすめ
脳科学で見る「怒られる子供のストレス反応」
脳科学的に見ると、厳しい叱責を受けると
扁桃体(恐怖・不安の中枢)が過剰に活動します。
この状態が続くと、
ストレスホルモン「コルチゾール」が慢性的に分泌され、
前頭前野(思考・判断)や海馬(記憶・学習)の働きを抑えてしまうのです[Lupien et al., 2009]。
つまり、「厳しすぎる=頭が良くなる」どころか、
脳のパフォーマンスを下げてしまうリスクがあるということ。
関連記事おすすめ
厳しさの中に“愛情”を残す関わり方
① 行動は否定しても「人格」は否定しない
「ダメな子!」ではなく、「その行動はよくなかったね」と伝える。
これだけで、子供は“自分は愛されている”と感じられます。
② 「理由」をセットで伝える
叱るときに「なぜいけないのか」を説明することで、
理性(前頭前野)を育てる学びの時間に変わります。
③ 「安心できる終わり方」を作る
叱ったあとは「でも、あなたが大事だよ」とフォローする。
叱る=関係が壊れるではなく、
安心の上に厳しさを置くことが信頼を育てます。
今日からできる「叱らないで伝える」習慣
- 「どうしたらうまくいくと思う?」と“考えさせる質問”に変える
- 「○○できたね!」と“できた部分だけ”を褒める
- 「怒る前に、深呼吸3秒ルール」を導入する
これだけで、家庭の空気がガラッと変わります。
関連記事おすすめ
まとめ|“厳しさ”よりも“信頼”が育てる力
子供を厳しくするほど、言うことは聞くかもしれません。
でもそれは“恐れ”による従順であり、“信頼”ではありません。
本当に強い子は、
叱られたあとでも「自分には価値がある」と信じられる子です。
「厳しさ」より「理解」
「ルール」より「信頼」
この順番を意識するだけで、親子関係は確実に変わります。
【関連記事】
【参考文献】
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. American Psychologist, 55(1), 68–78.
- Lupien, S. J., et al. (2009). Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. Nature Reviews Neuroscience, 10(6), 434–445.
- 厚生労働省. (2023). 児童のメンタルヘルスとしつけに関する調査報告書. https://www.mhlw.go.jp/
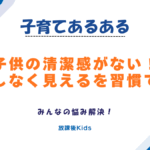
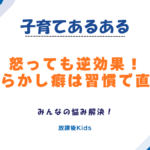
コメント