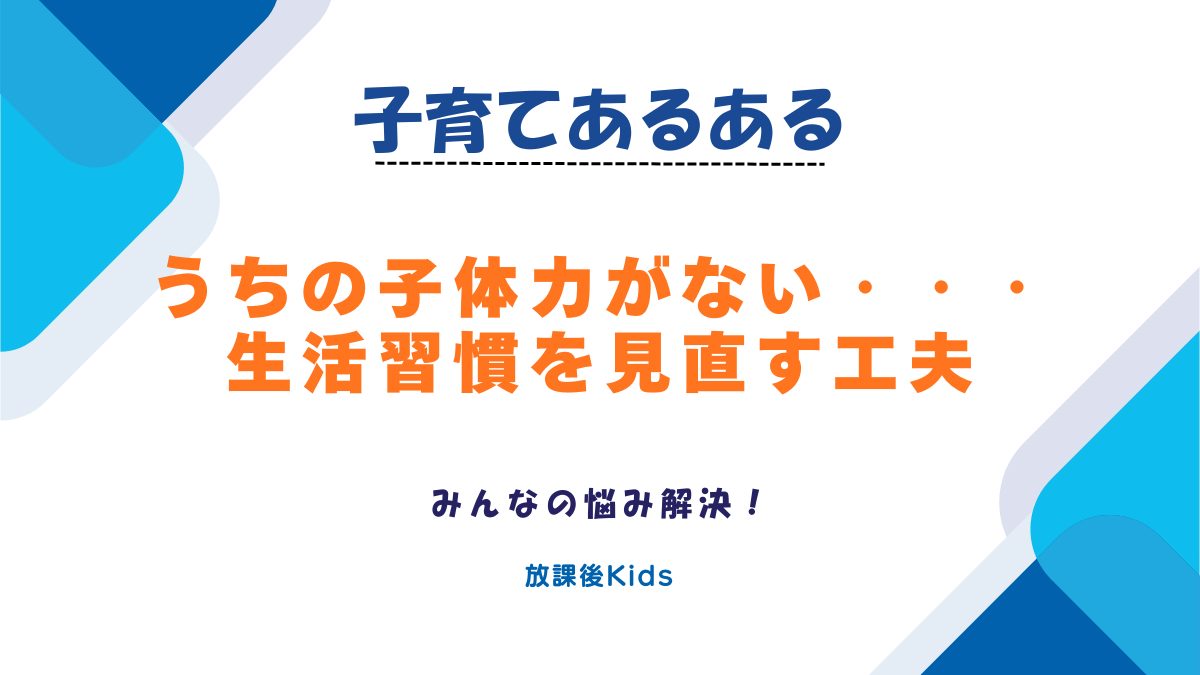
「少し歩いただけで疲れた」「体育のあと、すぐ休みたがる」
最近、子供の“体力のなさ”が気になる親御さんが増えています。
実際、文部科学省の調査でも、子供の体力はこの10年で顕著に低下しています。
その背景には、スマホ時間の増加・睡眠不足・外遊びの減少など、現代的な生活要因があります。
でももっと注目すべきは、
体力の低下が「学力」「感情の安定」「やる気」にまで影響していること。
この記事では、児童心理と脳科学の両面から、
“体力がない子に起きる心と脳の変化”をわかりやすく解説し、
家庭でできる実践的な改善法を紹介します。
データで見る「子供の体力低下」
文部科学省の「体力・運動能力調査」(2023)によると、
小中学生の体力はコロナ禍以降、10年前よりも平均値が大きく低下。
特に顕著なのが
- 持久走
- 握力
- 反復横跳び
といった“基礎体力”に関わる項目です。
原因の多くは「運動時間の減少」「スマホ・ゲームによる屋内生活の増加」「睡眠不足」。
体力低下は一見“運動の問題”に見えますが、実は脳と心の健康にも直結しています。
子供に体力がないと起こる3つの悪影響
① 集中力・学習意欲の低下
運動不足は脳の血流を減少させ、
海馬(記憶)や前頭前野(集中力・計画力)の働きを鈍らせます[Hillman et al., 2008]。
そのため、体力が低い子ほど「ぼーっとする」「やる気が出ない」などの傾向が見られます。
② イライラしやすくなる
体力が落ちると、自律神経のバランスが崩れやすくなります。
交感神経が過剰に働き、**“常に緊張・不安状態”**に。
結果、些細なことで怒りっぽくなったり、感情の波が大きくなるのです[厚生労働省, 2023]。
③ 自己肯定感の低下
体を動かす機会が減ると、達成感を得る場面も少なくなります。
「できた!」という経験が減るほど、脳内のドーパミン分泌も減り、
“自分に自信が持てない”状態に陥りやすいのです。
関連記事おすすめ
なぜ今の子は疲れやすい?生活習慣の落とし穴
- 外遊びの減少(安全・習い事・気候などの影響)
- スマホ・ゲームによる長時間座位
- 睡眠時間の短縮(平均6〜7時間台)
- 朝食抜きによる血糖バランスの乱れ
これらはすべて、自律神経の乱れ・体温リズムの崩れにつながります。
体力とは単に“筋力”ではなく、体のリズム全体を整える力。
つまり、生活リズム=体力の土台です。
関連記事おすすめ
体力と脳・心の深いつながり
脳科学的には、運動によって以下の物質が増えることが確認されています。
- BDNF(脳由来神経栄養因子):記憶力・思考力を高める
- セロトニン:心の安定・ストレス緩和
- ドーパミン:やる気・意欲の源
つまり「体を動かすこと」は、“脳を鍛えること”と同義なのです[Ratey, 2008]。
今日からできる!家庭での体力アップ習慣
① 毎日の「外時間」をつくる
1日15分でもOK。太陽の光と軽い運動で、体内時計とホルモンバランスが整います。
② 睡眠のゴールデンタイムを守る
22時〜2時は成長ホルモンが最も分泌される時間帯。
この時間に寝ていることで、体と脳の回復が進みます。
③ 家族で“動く習慣”を楽しむ
一緒に散歩・キャッチボール・ラジオ体操など、
「親が一緒に動く」ことが継続のカギ。
運動=楽しい時間、と脳が記憶します。
関連記事おすすめ
まとめ|体力づくりは“心の回復力”を育てる
体力とは、筋肉のことではなく「回復する力」。
ストレスや失敗を乗り越えるための、心と脳のエネルギーです。
子供の体力を育てることは、
「強い体」だけでなく、「折れにくい心」を育てることでもあります。
【関連記事】
【参考文献】
- 文部科学省. (2023). 令和5年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査. https://www.mext.go.jp/
- Hillman, C. H., et al. (2008). The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children. Neuroscience, 159(3), 1044–1054.
- Ratey, J. J. (2008). Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain. Little, Brown and Company.
- 厚生労働省. (2023). 子どもの生活習慣とメンタルヘルスに関する報告書. https://www.mhlw.go.jp/
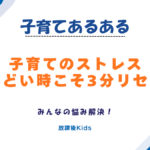
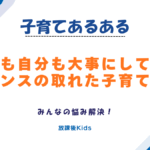
コメント