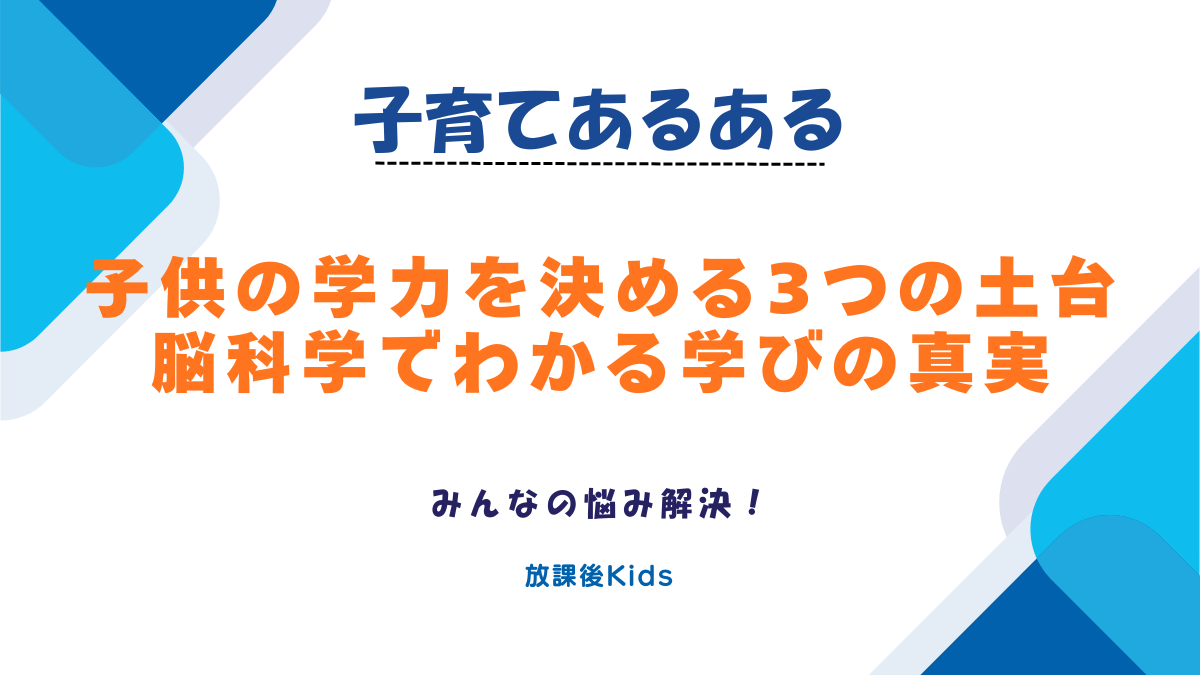
「うちの子、どうすれば学力が伸びるんだろう?」
──そう悩む親御さんは多いですよね。
でも実は、「勉強させる」よりも前に育てるべき“力”があるんです。
児童心理と脳科学の観点から言うと、
**学力とは「知識 × 脳の働き × 心の安定」**の総合力。
この記事では、10年以上児童福祉と教育現場に関わってきた心理士パパが、
「子供の学力を伸ばすために、今なにを伸ばすべきか?」をわかりやすく解説します。
学力=テストの点ではない
「学力=成績」と考えがちですが、
文部科学省の定義では、学力は以下の3つの要素から構成されています。
- 基礎的知識・技能(読む・書く・計算など)
- 思考力・判断力・表現力
- 学習意欲・主体性
つまり、「どれだけ勉強したか」よりも、
“学び続ける力”が本質的な学力なんです。
📎関連記事おすすめ
データで見る「学力を左右する要因」
東京大学・ベネッセ教育総合研究所の共同調査によると、
学力を高める要因として最も大きいのは「家庭環境」ではなく、
学習意欲と自己効力感(自分はできると思う力)でした。
さらに、
「失敗を恐れず挑戦できる子」は、学習量が少なくても学力が高い傾向にあります[Benesse, 2022]。
つまり
学力を伸ばしたいなら、
「勉強させる」よりも「挑戦を応援する」ことが近道なんです。
関連記事おすすめ
学力の土台を作る“3つの力”
① 集中力(前頭前野の活性化)
集中力は「脳の筋トレ」で伸びます。
毎日の小さな課題(本を10分読む・パズルを1問解く)で前頭前野が刺激され、
情報を整理する力が強化されます[Diamond, 2013]。
② 自己肯定感(失敗を恐れない心)
「どうせムリ」が口ぐせの子は、挑戦する前に学びを止めてしまいます。
小さな成功体験を積ませ、「やればできる」感覚を育てることが最重要。
心理学ではこれを自己効力感(self-efficacy)と呼び、
学習意欲・粘り強さに直結します[Bandura, 1997]。
③ 習慣化力(環境の力)
学力は“意志”より“環境”で決まります。
机の上を整える・同じ時間に学習する・親が横で読書する──
この「見本の環境」が、子供の脳に“学びの型”を刻みます。
関連記事おすすめ
家庭で育てられる学力の伸ばし方
1. 「勉強した?」ではなく「今日は何を学んだ?」
“行動”ではなく“中身”を褒める声かけが、
子供の内発的動機づけを高めます[Deci & Ryan, 2000]。
2. ミスを笑わない・責めない
失敗を恐れると、脳の扁桃体が働きすぎ、
学習効率が下がります。
「間違える=伸びている証拠」と伝えることが大切。
3. 親自身が“学ぶ姿”を見せる
子供は親の行動を“模倣学習”します。
親が読書や学びに興味を示すと、子供の脳内ミラーニューロンが活発化します。
関連記事おすすめ
まとめ|“勉強できる子”より“学び続ける子”に育てよう
学力は“点数”ではなく、“考え続ける力”。
焦らず、
「考える」「挑戦する」「失敗から学ぶ」──この3つを支えていけば、
どんな子でも学びを楽しめるようになります。
子供の“学力”を伸ばす前に、まず“学びたい心”を守ってあげよう。
【関連記事】
【参考文献】
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
- Benesse教育総合研究所. (2022). 学びの意欲と自己効力感に関する調査. https://berd.benesse.jp/
- 文部科学省. (2023). 学力の3要素に関する指針. https://www.mext.go.jp/
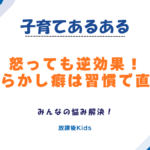
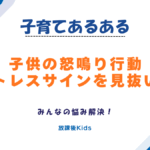
コメント