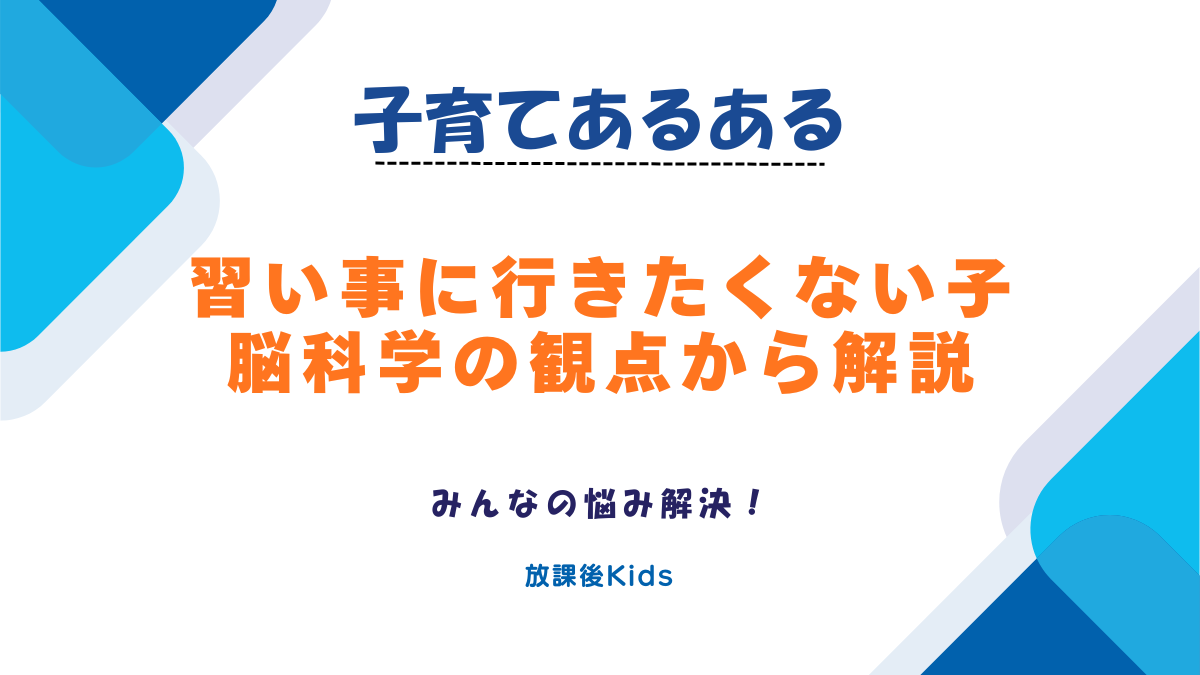
「せっかく習わせたのに、最近“行きたくない”ばっかり言う…」
「泣いて嫌がる姿を見ると、無理に行かせていいのか迷う」
そんな悩みを持つ親御さんはとても多いです。
10年以上、児童福祉の現場で子供の心と行動を見てきた経験から言えるのは、
“嫌がる=怠け”ではなく、“心がSOSを出している”ことが多いということ。
この記事では、子供が習い事をいやがるときに隠れている心理と、
親が今日からできる関わり方を、心理学と脳科学の観点からやさしく解説します。
子供が習い事をいやがるのは“甘え”ではない
親はどうしても「頑張らせなきゃ」「続けることが大事」と思いがちです。
でも実は、“いやがる”という行動は、子供の防衛反応なんです。
人間の脳には、「嫌なことを避ける働き(快・不快の制御)」があります。
つまり、子供の“行きたくない”には必ず理由があります。
📚関連記事おすすめ
習い事をいやがる子の3つの心理背景
① できないことへの不安
上達が遅い、友達より劣っていると感じると、脳は「逃げたい」と感じます。
これは自己肯定感の低下によるものです。
② 指導者や友達との関係ストレス
先生が怖い、友達が冷たいなど、“人間関係”のストレスが原因の場合も多いです。
特に小学生は、「誰とやるか」でモチベーションが変わります。
③ 家での安心時間の不足
学校・習い事・宿題でスケジュールがいっぱいだと、
「おうち時間=安心の回復」が足りず、拒否反応を起こします。
無理に行かせると逆効果?脳科学で見る“やる気の構造”
「やる気」はドーパミンという脳内物質で生まれます。
しかし、ストレスが強すぎるとコルチゾール(ストレスホルモン)が増え、
ドーパミンの働きを抑制してしまうのです。
つまり、「イヤイヤ行かせる」=「やる気を壊す」可能性があるんです。
📚関連記事おすすめ
我が家の失敗談と気づき
うちの次男(当時8歳)がサッカーを始めて半年後、「行きたくない」と泣きました。
最初は「甘えてるのかな」と思い、無理に連れて行きました。
結果、練習中に泣き、コーチに叱られ、完全に意欲を失ってしまいました。
その後、彼の話をじっくり聞くと——
「上手な子ばかりで恥ずかしい」「失敗するのが怖い」と。
そこで、練習を1回休ませて“おうちサッカー”を一緒に楽しむ時間を作りました。
2週間後、「また行ってみようかな」と自分から言い出したんです。
子供のやる気を取り戻す親の関わり方5ステップ
- まず話を聞く(否定しない)
「なんで行きたくないの?」より「どうしたの?」と受け止める言葉を。 - 原因を一緒に探す
人間関係?難しさ?疲れ?焦らず一緒に考えることが信頼につながります。 - 一時的な休息を認める
脳のストレスをリセットする“休み期間”を作ると、再挑戦の意欲が戻りやすい。 - 得意なところを言葉で強化する
「走るの速くなったね」「続けてるのすごいね」など、努力を認める言葉がやる気を育てます。 - 子供のペースで再スタートを提案
「週1回だけ」「見学から」など、再開のハードルを下げる工夫が効果的です。
📚関連記事おすすめ
まとめ|「続ける力」は安心から育つ
子供が習い事をいやがるとき、
それは“逃げ”ではなく、“心の安全を取り戻す反応”です。
親が一歩引いて受け止めることで、
子供の中に「またやってみよう」というドーパミンの火が自然と灯ります。
焦らず、責めず、信じて。
「やめる勇気」も「続ける力」も、どちらも成長の一部です。
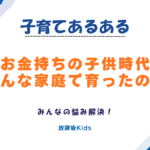
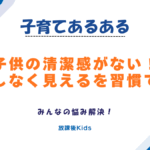
コメント