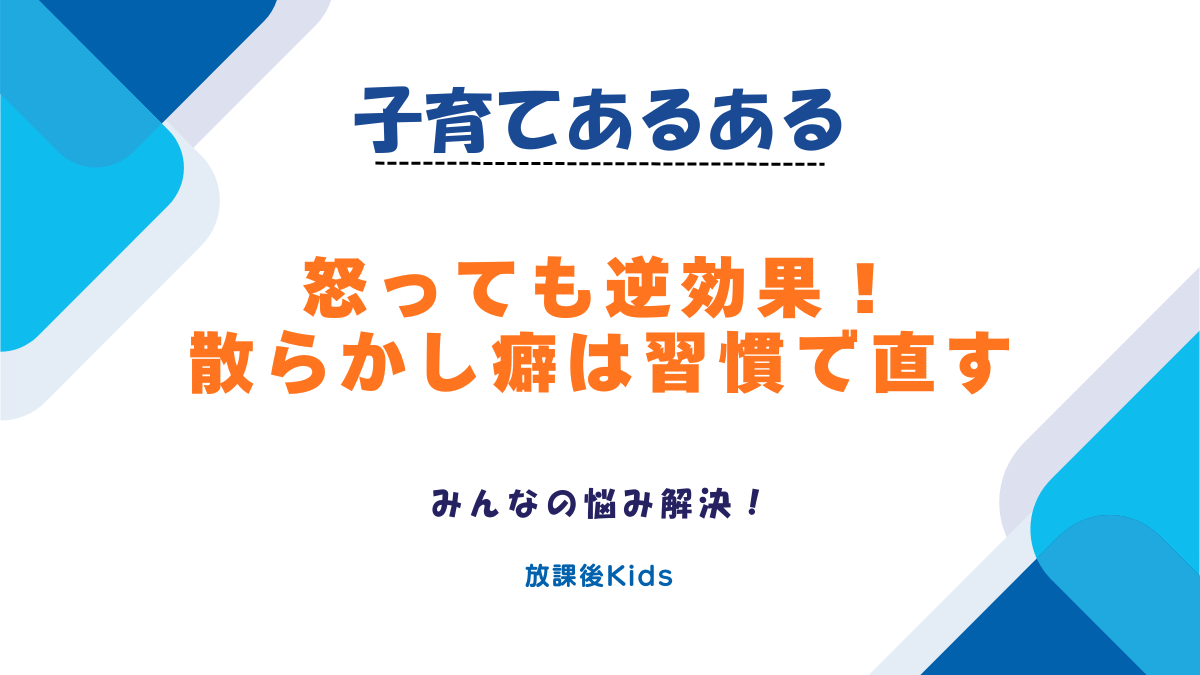
「もう何度言ったら片付けるの!」
リビングを見渡すと、ランドセルに靴下、おもちゃ、絵本が散乱…。
親としてはついイライラしてしまいますよね。
でも実は、“片付けない子”にはきちんと脳科学的な理由があるんです。
10年以上、児童福祉の現場で子どもたちの行動を観察してきた経験から言えるのは、
「片付けられない子」には、“意志の弱さ”ではなく仕組みの問題があるということ。
この記事では、心理学・脳科学・そしてリアルな子育て経験をもとに、
子供が片付けられるようになる考え方と、具体的なステップを紹介します。
子供が片付けをしないのはなぜ?
1. 「どこから片付けていいかわからない」
実は多くの子が、
「片付けたいけど、どうすればいいのか分からない」状態です。
片付けは「分類」「判断」「記憶」などの前頭前野の機能を総動員する高度な作業。
発達段階ではまだ未熟なため、大人が思うように動けないのは自然なことなんです[Diamond, 2013]。
2. 親が“代わりにやってしまう”習慣
忙しいとつい「もういい、ママがやる!」となりがちですが、
これが“片付けない脳”を強化してしまう最大の原因。
子供は「やらなくても誰かがやってくれる」と学習してしまい、
自発的な行動が育ちません。
📎関連記事おすすめ
親の「片付けなさい!」が逆効果な理由
心理学では、「強制される行動」より「自分で決めた行動」のほうが持続しやすいことが分かっています。
この現象を自己決定理論(Deci & Ryan, 2000)と呼びます。
つまり「片付けなさい!」と命令されると、
脳はストレスを感じ、反発のスイッチが入るんです。
「この箱とこの棚、どっちに入れる?」
「どっちの方がきれいに見える?」
こんな“選択型の声かけ”に変えるだけで、子供の行動が自然に変わります。
📎関連記事おすすめ
片付けができる子に育つ“脳の仕組み”
脳科学的にみると、片付けには実行機能(Executive Function)が深く関わっています。
これは、計画・注意・記憶・抑制などを司る前頭前野の能力です。
この力は一夜で身につくものではなく、繰り返しの習慣で強化されていきます。
また、片付け後に「スッキリした!」「褒められた!」という快感があると、
脳内でドーパミンが分泌され、行動が強化されることも分かっています[Kringelbach, 2015]。
今日からできる片付け習慣の作り方
①「片付けやすい環境」を整える
難易度が高いと続きません。
収納場所を減らす、ラベルを貼る、色で分けるなど、“見れば分かる”仕組みを作りましょう。
②「片付けスイッチ」を決める
「ご飯の前に」「寝る前に」「音楽を流したら」など、
条件反射型の習慣にすると忘れにくくなります。
③「小さな成功」を褒める
完璧を求めず、できた部分だけ褒めるのがポイント。
心理学的報酬である“承認”が、継続意欲を高めます。
📎関連記事おすすめ
我が家で効果があったリアル実践例
長女(7歳)の“片付けできない問題”は深刻でした。
毎晩、部屋はおもちゃの海。何度注意しても直らず…。
そこで始めたのが「ぬいぐるみ審査員制度」。
“うさぎ先生”というぬいぐるみを設定し、「片付けできたら先生がほめてくれる」というゲームに変えました。
最初はふざけていましたが、1週間後には
「先生に見せたいから片付ける!」と自発的に動くように。
遊びの要素を入れると、行動変化は加速します。
まとめ|片付けは「自立」のトレーニング
片付けを通して育つのは、
“自分の環境をコントロールする力”です。
叱るより、仕組みで支える。
焦らず、できた瞬間を一緒に喜ぶ。
それが、子供の「片付け脳」を育てるいちばんの近道です。
【関連記事】
【参考文献】
- Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
- Kringelbach, M. L. (2015). The pleasure of everyday things: Reward systems and motivation. Trends in Cognitive Sciences, 19(3), 99–105.
- 厚生労働省. (2023). 子どもの生活習慣形成に関する調査報告書. https://www.mhlw.go.jp/
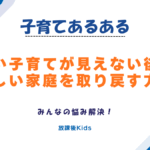
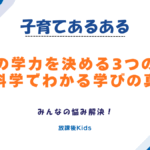
コメント