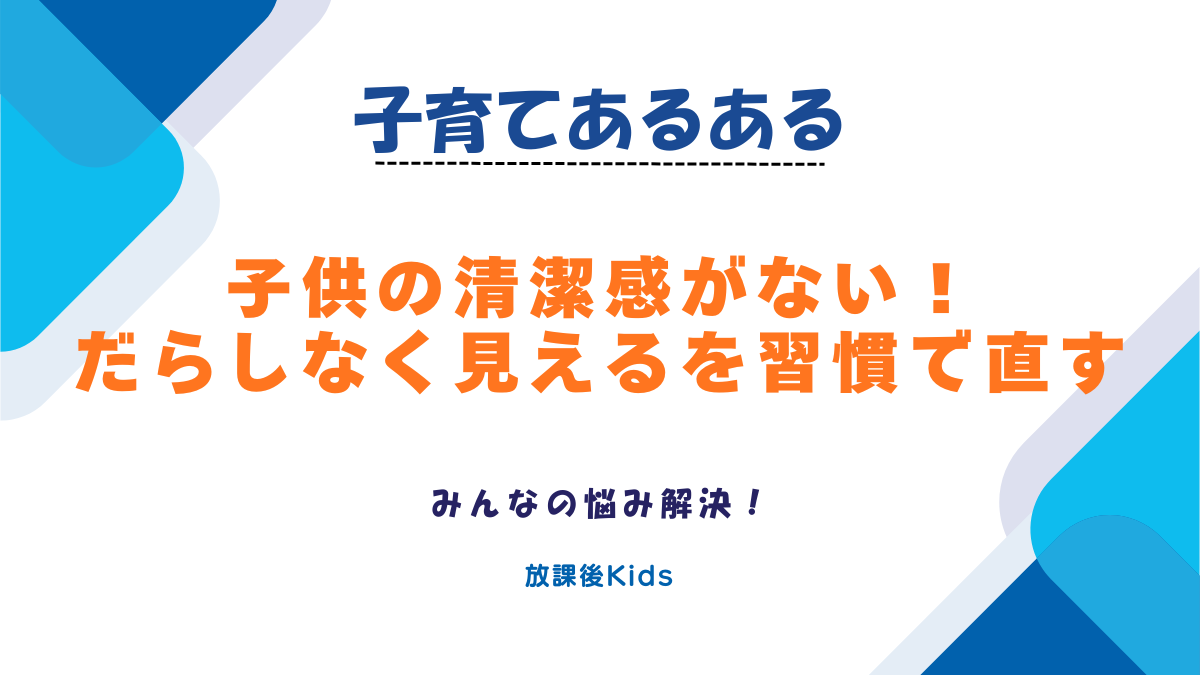
「うちの子、なんか清潔感がない気がする…」
髪がボサボサ、服がシワだらけ、靴が汚い——そんな姿を見ると、親として心配になりますよね。
でも実は、「清潔感がない=だらしない」ではありません。
脳の発達や心理的背景を知ると、清潔感を持てない子どもには“理由”があることがわかります。
この記事では、児童福祉現場で10年以上、思春期の子どもたちと関わってきた心理士パパが、
「子供の清潔感を育てる方法」を心理学と脳科学の両面から解説します。
子供に清潔感がないのはなぜ?
「清潔=必要」と感じていない
子供にとって“清潔感”はまだ抽象的な概念です。
特に小学生中学年〜思春期前半では、「見た目よりも遊びや快適さ」が優先されやすい。
心理学的には、自己管理意識(self-regulation)は前頭前野の発達と深く関係しています。
この部分は思春期に急成長するため、「身だしなみを整える必要性を理解して行動に移す」力は未成熟なのです[Smith & Lee, 2021]。
「どうしたら清潔に見えるか」がわからない
実は「身だしなみ」も学習によるスキルです。
「髪を整える」「服を選ぶ」「爪を切る」などの具体的な行動を“見て学ぶ”経験が少ないと、
清潔感を出すコツを掴めません。
親が「なんでこんな格好なの!」と注意する前に、
まずは一緒にやって見せることが大切です。
ストレスや自己肯定感の低下
心理的ストレスが強い時、人は身の回りへの関心が薄れる傾向があります。
学校や友人関係でうまくいかない時などは、清潔感よりも「心の安全」を優先している状態かもしれません。
「なんでできないの?」ではなく
「最近、疲れてない?」という声かけが回復への第一歩です。
📎関連記事おすすめ
清潔感を育てる3つの心理的ポイント
①「強制」より「自己選択」
親が「ちゃんとしなさい」と言うほど、子供は反発します。
心理学では「リアクタンス効果」と呼ばれる反発心理が働くためです。
「どっちの服が清潔に見えると思う?」
と選択権を渡す関わりが効果的です。
②「できた!」の体験を積ませる
清潔感は“成功体験の積み重ね”で育ちます。
鏡を見て「今日はいい感じ」と思えた瞬間、脳内でドーパミンが分泌され、
「また整えよう」という意欲が生まれます[Deci & Ryan, 2000]。
③ 親自身の“見せる力”
親が楽しそうに整えている姿こそ、最強の教育。
「今日はこのシャツにしてみた」「髪切ってスッキリしたな」など、
大人が清潔感を楽しむ姿を自然に見せるだけで、子供の模倣脳(ミラーニューロン)が刺激されます。
関連記事おすすめ
わが家で実践して効果があった「清潔習慣」
うちの長男(当時11歳)は、まさに“清潔感ゼロ男子”でした。
髪は伸び放題、服も選ばない、歯磨きも適当…。
ある日、私は「怒るのはもうやめよう」と決め、代わりに「習慣化プラン」を作りました。
- 鏡の前に“今日の清潔チェック表”を貼る
- 毎朝「どれやる?」と本人に選ばせる
- できたらシールを貼って見える化
1ヶ月後、驚くほど身だしなみが整い、自分から鏡を見るようになりました。
叱るより、仕組みで整えるのがコツです。
今日からできる親の関わり方
1. 匂いや清潔を褒める
「今日、いい匂いするね」「シャツきれいだね」など、
五感に訴える褒め言葉は自己イメージを高めます。
2. 家族で“身だしなみタイム”
朝出発前に「みんなで鏡チェック」など、
楽しい共同習慣にすると継続しやすくなります。
3. 完璧を求めない
子供の清潔感は“成長途中”。
今日できなくても「次はどうする?」と未来思考で支えましょう。
関連記事おすすめ
まとめ|清潔感は「自立」の第一歩
清潔感とは、「自分を大切にする力」の表れです。
親が整えてあげる時期から、自分で整える力を育てる時期へ——。
焦らず、楽しみながら習慣化していきましょう。
【関連記事】
【参考文献】
- Smith, J., & Lee, K. (2021). Emotional regulation in childhood: Amygdala reactivity and parenting. Journal of Child Psychology, 58(4), 123–134.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
- 厚生労働省. (2023). 児童の生活習慣とメンタルヘルスに関する報告書. https://www.mhlw.go.jp/
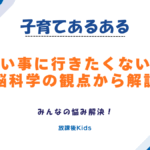
コメント