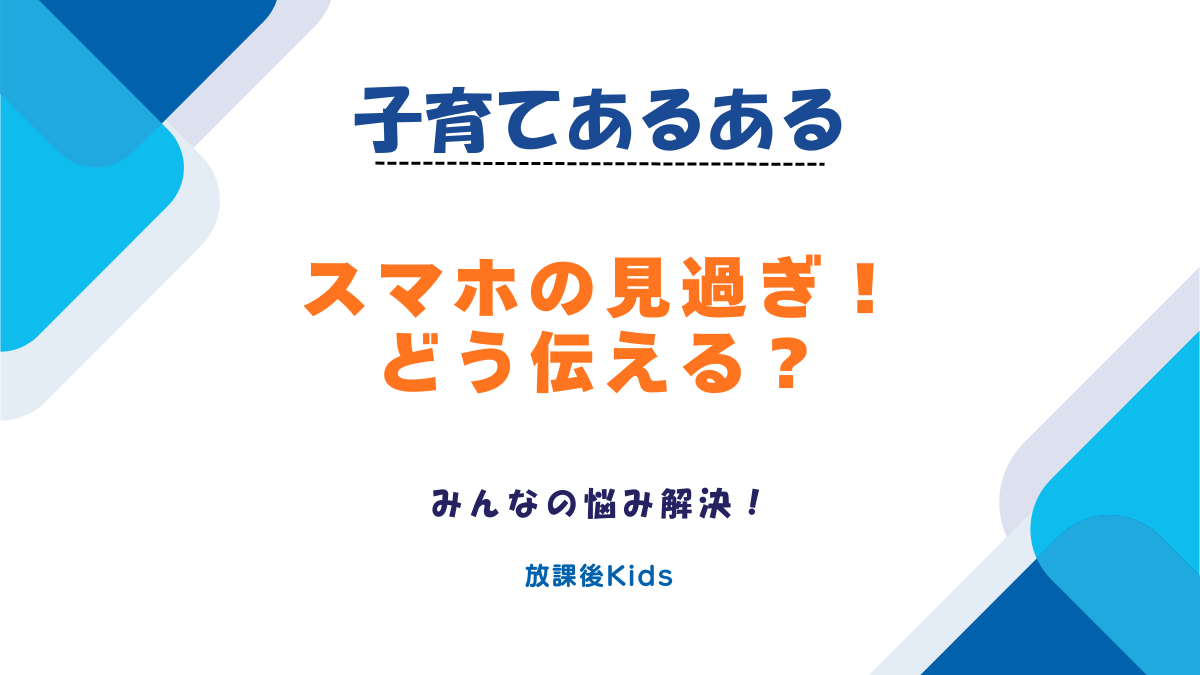
「うちの子、気づいたらいつもスマホ見てる…」
「注意しても全然やめない」
そんな悩み、ありませんか?
実は、スマホを“ずっと見てしまう子供”には、脳の仕組みと心のバランスが深く関係しています。
10年以上、児童福祉の現場で多くの子供たちと関わってきた経験から言えるのは——
「叱る前に、理解することが最初の一歩」ということです。
スマホ見すぎは「悪いこと」?それとも「SOS」?
多くの親が「スマホ=悪」と考えがちですが、実際は少し違います。
スマホは子供にとって「情報・交流・安心」を得るツールでもあります。
特に現代っ子は、学校や友達関係のストレスを、スマホで緩和していることが多いのです。
つまり、スマホに没頭する背景には、
- 寂しさ
- 承認欲求
- 自己コントロールの未熟さ
など、子供の心のバランスの崩れが隠れていることがあります。
「見すぎ=怠け」ではなく、「見すぎ=心のサイン」
と捉えることが、親としての第一歩です。
📚関連記事おすすめ
子供がスマホをやめられない3つの心理
① 報酬脳(ドーパミン)の快楽
SNSや動画の「いいね」「次の動画」は、脳にドーパミンを出します。
これが中毒的な快感を生み、「もう1回」「もう少し」と繰り返すんです。
② 承認欲求
「誰かに見てほしい」「繋がっていたい」——
子供は、まだ“自分の存在価値”を確かめる途中です。スマホは手軽な承認ツールになっています。
③ 現実逃避
学校や家庭でのストレス、友達との摩擦から逃げたいとき、
「スマホの世界は安全で自分を否定されない」場所に見えるのです。
スマホ依存にしないための親の関わり方
1.「取り上げる」より「一緒に見る」
いきなり制限をかけると、子供は反発します。
親子で一緒に動画を見たり、内容を話題にしたりすることで、“共感的コントロール”ができます。
2.「使用時間」より「使い方」を話す
何を見ているか?どう感じたか?を会話に。
使う時間よりも、「使う目的」と「気持ちの整理」が大事です。
3.「代わりの楽しみ」を提案
「スマホやめなさい」ではなく、
「一緒に散歩しよう」「ちょっと料理手伝ってくれる?」など、リアルの楽しさを思い出させる声かけを。
📚関連記事おすすめ
我が家の実例|スマホルールと“関係修復”のコツ
長男が中学生になった頃、夜中までスマホを触っていた時期がありました。
最初は叱りました。でも逆効果。反抗的になり、会話が減りました。
そこで方向転換。
「パパも一緒にスマホタイムにする?」と誘い、一緒に動画を観て感想を話す時間を作りました。
そのうち、「明日は早く寝たい」と自分から言うように。
ポイントは、
“管理”ではなく“共感”で距離を縮めること。
今日からできる小さな一歩
- スマホを否定せず「何を見てるの?」と声をかけてみる
- 食事中だけはスマホを置く“家族ルール”を一緒に作る
- 親もSNS時間を少し減らす(モデリング効果)
まとめ|スマホ時間は“敵”ではなく“関係の鏡”
子供のスマホ時間は、親子関係のバロメーターでもあります。
「スマホばかり見てる!」と怒る前に、
「この子、今どんな気持ちで見てるんだろう?」
と一度、心の目で見てみてください。
それだけで、子供の世界が少しずつ見えてきます。
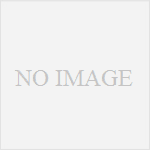
コメント